「恩は本人に直接返さなくていいのですか?」
「恩送りは何から始めればいいの?」
「恩返しと恩送りの違いは?」
恩返しとは、受けた恩をその本人に返すことです。一方、恩送りは受けた恩を別の人につなぎ、感謝の輪を広げる行為を指します。

とはいえ、どう実践すればよいか迷う方も多いでしょう。
そこで本記事では、以下の内容を解説します。
- 恩送りの意味
- 恩返しとの違い
- 恩送りのメリット
- 実践のやり方と押さえるべきポイント
この記事を読めば、恩送りの具体的な方法が明確になり、すぐに行動へ移せるようになります。ぜひ最後までご覧ください。
恩送りを実践するためには、感謝の気持ちを深めることが大切です。感謝の心を高めたい方には、5日間にわたって無料で学べる「予祝5DAYSチャレンジ」が役立ちます。
4日目には「感謝を深めるワーク」があり、恩送りの実践につながるヒントを得られます。その体験を通じて、恩送りに対する気持ちも自然と変わっていくでしょう。
詳細は、以下のボタンから確認してください。
恩送りとは?概要をサクッと解説

恩送りを理解するには、まず基本となる考え方を押さえておくことが大切です。
ここでは、恩送りに関する3つのポイントに分けて解説します。
- 恩送りとは
- 恩は感謝があってこそできるもの
- 恩返しと恩送りの違い
この3つを理解することで、恩送りの全体像がよりイメージしやすくなります。それでは、順番に見ていきましょう。
1.恩送りとは
恩送りとは、自分が受け取った恩や優しさを、直接の本人ではない別の誰かに返していくことです。
たとえば、部活動で先輩から受けた恩を、今度は後輩へのサポートとして返すことが当てはまります。ほかにも、学校の先生に助けられた経験をきっかけに、自らが教師となり今度は自分が生徒を支える人のケースもそうです。

実は私たちは、身近な人だけでなく、過去の多くの人々からも恩を受けています。私たちが便利に使っているものも、多くの人の努力のおかげです。
たとえば次のような製品は、先人たちの頑張りがあったからこそ、今の私たちの生活を支えています。
- 飛行機:ライト兄弟が発明
- 電球:エジソンと研究チームが開発
- iPhone:スティーブ・ジョブズと開発チームが製作
とくにiPhoneの開発では厳しいチェックが重ねられたとされます。その苦労のおかげで、私たちはiPhoneによって快適な生活を送れています。
医療や教育、交通インフラを安心して利用できるのは、多くの人々のたゆまぬ努力のおかげです。それらを「あって当たり前」と思うか、「多くの人のおかげで利用できるんだなぁ、ありがたい!」と感謝するのでは、未来は大きく変わります。
自分は多くの人から恩を受けていることを忘れずに、新たな誰かに返していく姿勢こそが、恩送りの本質です。
2.恩返しと恩送りの違いとは
恩返しと恩送りの違いは次の通りです。
- 恩返し:受けた恩を本人へ返すこと
- 恩送り:受けた恩を別の人へ与えること
たとえば、小学校時代、いじめにあったときに学校の先生に助けられたとします。その先生に感謝の手紙を送ったり、将来、結婚式に招待したりするのは恩返しです。
恩返しは「恩を受けた相手を幸せにしたい」という想いから生まれます。

恩送りは「受けた恩を誰に返したい!」という想いに加え、「あの先生のようになりたい!」という憧れの気持ちから生まれる場合もあります!
また、大切な人に恩返しできなかった経験から、その罪悪感の気持ちから恩送りを実践する人もいます。このように恩返しは直接的な行動、恩送りは間接的に広がる行動であり、どちらも誰かのために行う大切な習慣です。
3.恩送りは感謝があってこそできるもの
恩送りを理解するには、まず「恩」と「感謝」の関係を知ることが大切です。

ちなみに日常生活の中にも、感謝を抱く瞬間は多くあります。
たとえば、次のような場面です。
- 人に助けてもらったとき:「手伝ってくれてありがとう」と感謝する
- 電車に乗れるとき:「日本は移動が楽でありがたい」と感じる
- 夏場にクーラーが使えるとき:「江戸時代と違い、夏でも涼しい環境にいれて助かるな」と思える
感謝は、相手がいてもいなくても感じられるものです。一方、恩を返せるのは相手が存在する場合に限られます。
人に助けてもらったときは恩返しができても、電車やスマホといった環境や物には、基本的には返せません。
昔話「浦島太郎」では、浦島太郎がいじめられていた亀を助けたからこそ、亀は竜宮城へ案内するという恩返しをしました。しかし、もしいじめられたのが人形だったら、同じような結末にはならなかったでしょう。
恩は、相手との関わりがあってこそ成り立つのです。
ちなみに、関連記事「「既にある」が潜在意識に腑に落ちた!実感すると引き寄せを実感しやすくなる理由とは」では、感謝の心を育むための方法をお伝えしています。恩送りを深く理解するヒントをつかむためにも、ぜひお読みください。
恩送りとは?実践する3つのメリットを解説

恩送りを実践すると、自分自身だけでなく周りの人にも良い循環が広がります。
その中でも特に大切な3つのメリットを見ていきましょう。
- 自分の人間性が磨かれる
- 思いやりの輪が広がる
- 巡り巡って恩が返ってくる
この3つを意識すると、恩送りの魅力がぐっと実感しやすくなります。それぞれを詳しく見ていましょう。
1.人間性が磨かれる
恩送りを実践すると、自分の人間性(あり方)が磨かれます。相手から受けた恩を誰かに返そうとする行為は、多くの人の心を打つ美しい行為です。

恩送りは見返りを求めず、報酬がなくても相手のために行います。見返りがなくても恩を忘れずに行動できる人は、周囲から信頼され、人としての魅力が高まります。
多くの成功者は、受けた恩を忘れずに誰かのために役立とうと行動します。その姿勢こそが、成功を引き寄せる大きな要因と言えるでしょう。
だからこそ、恩送りは自分の人間性を磨くのにおすすめな行為です。
2.思いやりの影響が広がっていく
恩送りとは、相手のために自分の時間や労力を差し出す行為です。その結果、人の役に立てたという充実感が得られます。
たとえば、誰かに受けた恩を返すために、お年寄りに席を譲ったとしましょう。すると、お年寄りから「ありがとう」と感謝され、自分も温かい気持ちになります。
この温かい気持ちを繰り返し経験することで、「自分は人の役に立っている!」という実感が芽生え、セルフイメージも高まります。小さな親切でも、その行為が連鎖していきます。
この連鎖を説明する比喩として有名なのが「バタフライ・エフェクト」です。

これは、わずかな影響が大きな結果を生むことを示しています。
同じように、思いやりの行動は小さくても、その影響は広がっていきます。だからこそ、小さなことでも恩送りを続けることが大切なのです。
3.巡り巡って恩が返ってくる
恩送りを続けていると、やがて何らかの形で恩が返ってきます。

これは、いつ恩が返ってくるかは分かりません。
たとえば、先輩に受けた恩を感じて後輩に恩送りをした場合、返ってくるのはその後輩ではなく、全く関係のない人の可能性があります。
この巡りのタイミングは予測できませんが、必ず返ってきます。だからこそ、恩送りには1つの無駄もないのです。
恩送りに関連する名言とそれを活かす方法
恩送りの精神をよく表す名言として、古代ギリシャの寓話作家イソップの言葉があります。
“No act of kindness, no matter how small, is ever wasted.”
「どんなに小さな親切も無駄になることは決してない」
この言葉は、小さな思いやりは必ず何らかの形で意味を持つことを意味しています。では、この考えを日常に活かす例を見てみましょう。
たとえば、好きな人に告白する場面を想像してください。結果がうまくいかず、断られることもあるでしょう。

すると、望んだ結果でなくても、後々プラスの影響が生まれることがあります。
この気持ちでいれば、相手と良い関係を築くための行動が自然にできます。その状態になると、その人のために理解者になろうと寄り添い、気持ちに耳を傾けるようとするでしょう。
そのときに、たとえ振られたとしても「自分がやったことは無駄じゃない!きっと誰かが喜んでくれる!」と与える姿勢を持ち続けることがポイントです。
その後、相手から「やっぱり付き合いたい」と言われることもあります。また、その経験を誰かに話すことで「あなたの話を聞いて勇気が出た!」と感じる人が現れることもあります。
こうした行動の連鎖も、恩送りの一つの形です。
なお、恩送りを実践するためには、誰かが喜んでくれる姿を思い描くことも大切です。そのイメージを持つことで、恩送りをしやすくなります。
そのために役立つのが、5日間無料で学べる「予祝5DAYSチャレンジ」という講義です。こちらに参加することで、相手にどんなことを与えられるのかをイメージしやすくなります。
この講義を実践することによって、恩送りへの向き合い方も自然に変わっていくでしょう。
必要なのは紙とペンのみです。詳細は、以下のボタンからご確認ください。
恩送りを生活に取り入れるやり方とは

恩送りを始めたいと思ったら、まず具体的な方法を決めましょう。
「どんな形で親切をできるか?」と自分に問いかけ、次のようにリスト化してみます。
- 電車でお年寄りに席を譲る
- 少額でも募金をする
- 店員さんに「ありがとうございます!」と伝える
- お世話になった学校の先生に感謝の手紙を送る
- 友達のFacebook投稿に「いいね」やコメントをする
- 月に一度ゴミ拾いをする
- ボランティアに参加する

ポイントは、小さな親切から始めることです。たとえ小さくても繰り返すうちに、恩送りは習慣になります。
もし具体的な行動が思いつかない場合は、「予祝キャラバン」というイベントのボランティアスタッフとして参加するのもおすすめです。ボランティアとして応援すると、誰かの役に立っていると実感が湧きやすくなります。
なお、関連記事「大嶋啓介の予祝キャラバン講演会・イベントレポート!情熱の2時間(2024年神奈川版)」では、予祝キャラバンの様子を詳しく紹介しています。あわせてご覧ください。
恩送りを実践するときにおさえておきたい3つのポイントとは

恩送りを実践するうえで大切な3つのポイントを紹介します。意識して取り入れることで、自分自身の成長につながるヒントになります。
- 命を尊重する
- 悪い行いは悪い形で返ってくる
- 素直な気持ちがそのまま返ってくる
それぞれを具体的に説明していきましょう。
1.命を尊重する
恩送りを行ううえで、相手の命を尊重することは欠かせません。
そのうえで、以下の2つのポイントを理解することが大切です。
5-1.命が限りあることを意識する
目の前の相手が限りある命であることを意識することが大切です。この意識が芽生えると自然と思いやりの行動が増えて、恩送りをする数が増えます。
人は、自分にとって都合のいい情報や利益を求めがちです。恋愛なら、タイプの人を見たときに「この人と付き合いたい」と思うことがあります。
職場や友人関係でも、自分に利益がある相手にだけ親切にしようとする場面は少なくありません。

自分が認められたい、相手から何かを受け取りたいと思うなら、まずは自分から与える姿勢を大切にしましょう。
5-2.素直に接して信頼関係を築く
命を尊重するとは、相手を父と母から授かったかけがえのない存在として敬うことです。そのためには、自分を飾らず素直に見せることが大切です。
相手に良いところだけを見せて欠点を隠すと、偽りの関係が生まれて、信頼関係を築く機会を失う場合があります。
たとえば、一緒に旅行をしているときに、オナラをしてしまうなど格好悪い弱みを見せることもあるでしょう。しかし、最初から弱みや恥ずかしい一面を素直に出せれば、相手も「この人なら本音で話せる」と感じ、信頼が深まります。

信頼があるからこそ、恩送りを実践する土台が整います。だからこそ、相手を尊い命として敬い、素直に接していく姿勢を忘れないようにしましょう。
2.悪い行いは悪い形で返ってくる
恩送り、つまり他人に親切を続けていれば、いずれ恩が返ってきます。一方、良い行いが返ってくるのと同じように、悪い行いは悪い形で返ってくる場合があります。
たとえば、AさんはBさんと7月31日の15時に会う約束をしていました。ところが、Aさんの恋人から「大事な話がある」と言われ、当日になってBさんに予定変更を依頼しました。
Bさんからすれば、急な変更に「なんだよ!」と感じるかもしれません。
相手の立場を考えないことを繰り返していると、Aさん自身も友人と会うときに当日に相手から変更を求められたり、体調不良で予定が流れたりするケースが増えていきました。

日ごろから言動に気をつけ、悪い行いをしていない注意を払いましょう。
3.素直な気持ちが返ってくる
恩送りは行動の裏にある素直な気持ちが、そのまま相手に返ってきます。

たとえば、次のコンビニの店員のあいさつを比べてみましょう。
この違いだけで、受け手の印象が変わります。笑顔でのあいさつは無意識に「いい雰囲気の店だ!」とお客様が感じられるようになり、再来店や口コミにもつながります。
もしお客様が落ち込んでいたなら、自分の存在を認められたような温かさを感じてもらえるケースもあるでしょう。
あいさつは単なる接客ではなく、小さな親切の一つです。たった一言でも場の空気を和らげ、相手の気持ちを前向きに変える力があります。
笑顔や声のトーンに込めた気持ちは、相手の心の気持ちを温かくし、いい影響を与えます。一方、義務的な態度では、お客様の心に響くことはないでしょう。
ポイントは、恩送りをする際は誰に対しても心から接することです。その素直な気持ちが返ってくる恩送りにつながります。
ちなみに、関連記事「宇宙の法則をわかりやすく紹介!引き寄せの法則を効果的に使う7つの方法を徹底解説!」では、実践したことが親切が返ってくる具体例を用いて解説しています。ぜひ、あわせてご覧ください。
感謝の心を育てて恩送りを後押しする予祝5DAYSチャレンジとは
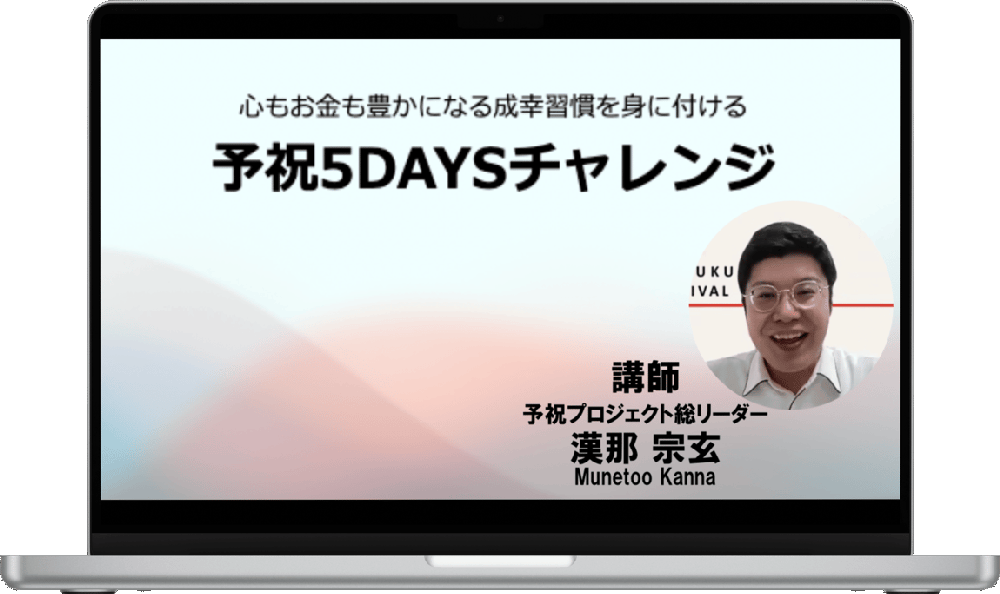
恩送りを意識して親切を続けると、自然と人間性は磨かれていきます。とはいえ「どうやって恩送りをすればいいのか分からない」という方もいるでしょう。
そこでおすすめなのが「予祝」です。予祝は未来の喜びを先に祝うことで、良い気分になり、明るい現実を引き寄せるメソッドです。
この考え方は、日本の花見が由来といわれます。

この予祝はいい未来を引き寄せるだけでなく、今ある恵みに気づきやすくなります。その気づきが感謝を育み、やがて誰かに恩を渡す行動(恩送り)につながります。
この予祝を実際に体験できるのが「予祝5DAYSチャレンジ」です。5日間で予祝のやり方を学べる無料講義で、必要なのは紙とペンだけ。
4日目の感謝のワークでは、とくに恩送りのイメージを描けるヒントがあるので見逃せません。ぜひ以下のボタンから詳細をご確認ください!




