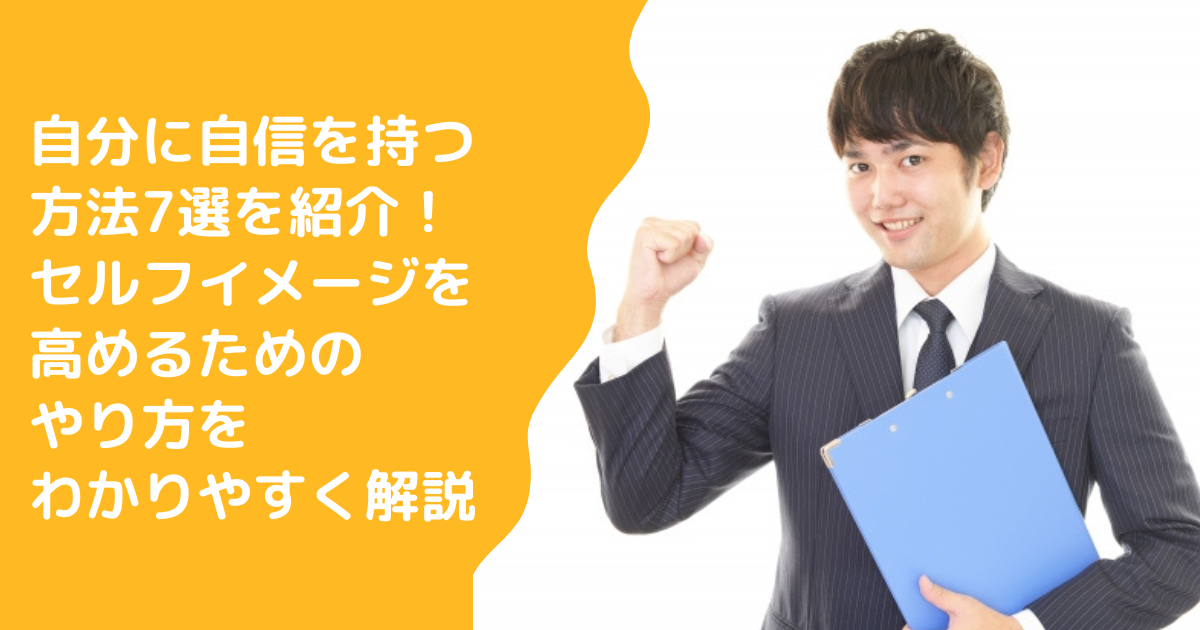「辛いことがあると、すぐに現実逃避してしまう」
「根性がない自分をクズだと思ってしまう」
「逃げ癖を改善する方法を知りたい」
逃げ癖を直したいと思っても、いざとなると現実逃避してしまう人は多いものです。しかし、逃げ癖で自分をクズだと思っても克服した人はたくさんいます。

だからこそ、逃げ癖の原因や対処法を知ることが大切です。
この記事では以下のことをわかりやすく解説します。
- 逃げ癖でクズだと思ってしまう原因
- 対処法
- 知っておきたいポイント
- 逃げ癖から抜け出せた事例
逃げ癖を乗り越えるヒントが得られますので、ぜひ最後までお読みください。
なお、逃げ癖を改善するには、思考パターンを変えることが重要です。それを具体的にいうと、機嫌を良くすることです。
逃げたくなるときは気分が沈み、新しいチャレンジを避けがちですが、機嫌が良ければ困難にも立ち向かえます。
そこでおすすめなのが、「予祝5DAYSチャレンジ」という5日間にわたる無料講義です。この講義は、理想の未来を描くワークを実践することで、落ち込みやすい気分を前向きに変えるきっかけになります。
詳細は、以下のボタンからから確認してください。
逃げ癖でクズと思っても直せない3つの原因

逃げ癖が直らないのには理由があります。
主な原因は次の3つです。
- 責任を重く捉えすぎている
- 経験と知識が不足している
- 思い込みが現実を引き寄せる
これらを理解すれば、逃げ癖がある自分はクズだと自己嫌悪に陥る原因がわかります。
1.責任を重いものと捉えている
逃げ癖がある人は、責任を重く捉える傾向があります。
責任に対して「重い」「怖い」といったネガティブなイメージを持ちすぎているため、大事な決断ができません。成果を上げるより「自分のせいにされたくない」という気持ちが強いのです。
しかも、この自己中心的な考えを自覚しているため、「逃げてしまう自分はクズだ」と自己嫌悪に陥りやすくなります。責任を重く捉えているからこそ、プレッシャーに耐えきれなくなるのです。
2.知識と経験が不足している
逃げ癖の原因は、知識と経験が不足していることです。
たとえば、化粧品会社で初めてクライアント向けのプレゼンを任されたとき、緊張で頭が真っ白になることがあるでしょう。失敗すれば「もう二度とプレゼンなんてやりたくない!」と逃げ腰になるのは当たり前なことです。

十分な知識とプレゼン経験を積めば、たとえ緊張してもある程度のプレゼンはできるようになります。
3.思い込みが現実を引き寄せる
私たちの現実は、自分の思い込みに大きく左右されています。
「お金を稼ぐのは大変だ!」と思い込んでいる人は、実際に苦労してお金を稼ぐことになりがちです。同様に「自分は逃げ癖があるクズだ!」と信じ込んでいると、そのような行動パターンを繰り返してしまいます。
この思い込みを外すコツは、違う価値観を持つ人との出会うことです。
たとえば、楽しくスムーズにお金を稼ぐ人と接することで「こんな生き方もあるんだ」と新しい可能性に気づける場合があります。さまざまな人と関わることで心の制限を外れ、思い込みから解放されて新しい自分に出会えるはずです。
ちなみに、関連記事「逃げ癖が手遅れになってしまう4つの原因とは?克服して未来を変える方法も紹介」では、逃げ癖が手遅れになってしまう原因について解説しています。逃げ癖の原因を深く知りたい方は、あわせてお読みください。
逃げ癖でクズだと思ったときの対処法4選

「もう逃げたくない」と決意したあなたへ、現実を変える4つの方法をお伝えします。
- 鏡に向かってアファメーションする
- スキルを1.5流まで身につける
- メンターを作る
- 予祝をする
この中から、できそうなものを選んで始めてみましょう。
1.鏡に向かってアファメーションする
鏡の中の自分に笑顔で、アファメーションをしていきましょう。アファメーションとは、自分に対して前向きな言葉を繰り返し伝えることで、思考や価値観をポジティブな方向へ導く方法です。
具体的にいうと「あなたは素晴らしい!」と話しかけ続けると、誰かに褒められたような気分になります。

すると、少しずつ安心感が積み重なり、不安が和らいでいきます。
アファメーションのポイントは、自分が言われて嬉しい言葉、安心する言葉をかけることです。
例として、次のような言葉がおすすめです。
- あなたは一流だ!
- あなたはカッコイイ!
- あなたは努力家だ!
自分が褒められて嬉しい言葉を毎日続けることで自己肯定感が高まり、自分をクズだと思う状況から抜け出しやすくなります。
なお、関連記事「【【朝・夜3分】アファメーションで人生が変わったと感じた体験談3選を紹介!やり方も徹底解説」ではアファメーションの作り方の参考になります。実践したい方は、ぜひご覧ください。
2.スキルを1.5流まで身につける
逃げ癖を克服する方法は「自分だけの強み」を作ることです。
たとえば、強みの例として、以下のものがあります。
- SNSの知識がたくさんある
- 動画編集ができる
- 歴史をたくさん語れる
何か一つでも得意分野を持つと自信がつきます。
大切なのは、いきなり1流を目指すのではなく「1.5流」を目指すことです。1流を目指すとなると難しいと感じますが、1.5流のやや詳しいレベルなら達成しやすくなります。
少しずつ経験を積み重ねて、1.5流レベルにスキルを磨けたときは「逃げない自分」になれているはずです。
なお、関連記事「自分に自信を持つ方法7選を紹介!セルフイメージを高めるためのやり方をわかりやすく解説」では、自信をつける方法について解説しています。知識と経験を身につける方法を参考にしたい方は、あわせてご覧ください。
3.メンターを見つける
一人で頑張り続けるのは容易なことではありません。そんなときは、自分を引っ張ってくれるメンターの存在が重要です。
たとえば、ダイエットのCMで有名なパーソナルジムで痩せられるのは、トレーナーが食事など生活習慣をチェックしてくれるからです

メンターを探すには、次のような方法があります。
- オンライン・サロンに入る
- SNSで探す
- セミナーを受ける
見つけるコツは「自分がこうなりたい!」「このような人になりたい!」という視点で検索することです。
4.予祝をする
逃げ癖がある人こそ、予祝(よしゅく)をおすすめします。
予祝とは、理想の未来をすでに叶えたかのように祝うことで、脳に成功のイメージを刻み込む日本古来の方法です。昔の日本では、お花見は「秋の豊作を前もって祝う行事」として行われていました。
その事例として、俳優の武田鉄矢さんには、こんなエピソードがあります。彼は芸能界を目指して上京したものの、うまくいかず実家に戻りました。
そんな彼に、母親が「鉄矢、成功おめでとう!」と笑顔で乾杯してくれました。当時の武田鉄矢さんは、その意味が分からなかったものの、不思議な気持ちで一緒に乾杯しました。
その後、再び上京すると、今度は芸能界で成功を収めたのです。これは母親と一緒にした「予祝」が現実を引き寄せたとも言われています。
予祝をすると「すでに成功した自分」を思い描けるようになるので、逃げたい気持ちよりも「やってみよう!」という前向きなエネルギーが湧いてきます。
「このままでいいの?」「本気を出すのはいつ?」と感じている方ほど、予祝を試してみてください。
ちなみに、この予祝を実践できるのは「予祝5DAYSチャレンジ」という5日間にわたる無料講義です。自分をクズだと評価してしんどい方は、以下のボタンから確認してください。
逃げ癖によってクズだと思ったときに知っておきたい3つのポイント

逃げ癖があっても、自分をクズだと決めつける必要はありません。考え方を変えれば、新しい可能性が開けてきます。
そこで、発想を転換する3つのポイントを紹介します。
- 責任の解釈を変える
- 三日坊主は良い解釈にも変えられる
- 失敗は成功を生み出すためのヒントである
これらの視点を持つことで、自己否定から抜け出しやすくなるでしょう。
1.責任の解釈を変える
「責任を取ると自由が手に入る」という考え方があります。多くの人は「責任=重い負担」と捉えがちですが、実際は逆です。

たとえば、責任を取ることには、以下のようなメリットがあります。
- 働き方を選べる
- 仕事と休みのバランスやルールを決定できる
- 自分の報酬を決められる
つまり、責任を取るほど、自由度が上がっていくのです。
ちなみに、責任を持つと何が足りないか見つめ直すようになり、ほしいものを本気でリサーチするようになります。計画を練って課題に向き合うので、経験やスキルが身につきます。
ポイントは、まずは大きな責任ではなく小さな責任から始めることです。責任を取る癖がつけば、次第に大きなことでも責任を取って行動するようになるでしょう。
2.三日坊主は良い解釈にも変えられる
三日坊主は決して悪いことではありません。料理が苦手な人でも、カレーを3日間作り続ければ、おいしく作れるようになります。
三日坊主を33回繰り返して、もう1回行えば100日になります。一度続けられなくても、何度も挑戦すればいいのです。
大切なのは「完璧に続ける」ことではなく「小さくても始め直す」ことです。三日坊主は挑戦した証です。失敗しても、「また挑戦すればいい」という軽い気持ちで、何度でもチャレンジしましょう。
なお、関連記事「潜在意識が変わるときの3つの前兆を紹介!理想を叶えるヒントになる3つの考え方もご紹介」では、継続について解説しています。どれだけ続ければ、効果が出るか知りたい方は、ぜひご覧ください。
3.失敗は成功を生み出すためのヒントである
「失敗は成功を生み出すためのヒント」という言葉には、深い意味があります。
誰も失敗しようと思って行動する人はいません。 失敗したということは、行動や考え方のどこかに間違いがあったという発見です。
具体例を挙げると、エジソンは電球を発明するまでに1万回以上失敗したと言われています。

つまり、失敗は新しい学びを得るチャンスです。そこで失敗したとしても、「次はどうすればうまくいくか」のヒントとして受け取りましょう。
失敗を分析することで、自分の改善点が見つかり、次の成功につながります。
逃げ癖でクズだと思う自分から抜け出せた高橋理恵子さんの成功事例

予祝講師の高橋理恵子さんは、幼い頃から「のろま」というレッテルを貼られ、自信を失っていました。「理恵子は、洗濯物の仕事がのろいから、お姉ちゃんお願いね」という言葉を日常から家族に言われていたそうです。
姉と比べられ続けた結果、「のろい自分はダメなんだ」と自信をなくしていました。
その結果、何かうまくいかないことがあると、すぐに諦める理由を探すようになりました。自分が傷つかないように、挑戦から逃げることで心を守っていたのです。
しかし、「このままの自分じゃ嫌だ!変わりたい!」という強い思いが湧き上がりました。

その憧れの気持ちから、高橋理恵子さんは、予祝講師養成講座を受講しました。すると、予祝のイベントで新人賞を受賞したそうです。
彼女の成功の秘訣は「ピンチの時こそ全力で面白がる」というポリシーを作ったことでした。逃げたくなる場面でも、この言葉を思い出して「今はこの出来事を面白がってみよう」と考えられるようになりました。
今では過去の自分に対して「いつまで諦めているんですか?いつまで逃げるんですか?自分のことを信じて貫いてね!一緒に突き進みましょう!」と言いたいそうです。
ここまで高橋理恵子さんが変われたのは、予祝講師になり自分を磨いたからでした。そこで、逃げ癖を直すために自分を磨きたい方は、予祝講師養成講座の体験会への参加をおすすめします。
体験会は無料ですので、ぜひ参加してみてください。
※なお、予祝講師講座の成果には個人差があります。